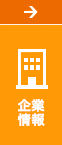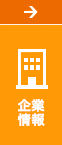知っておきたい ふすま(襖)の使い方
- ふすま(襖)とは
- ふすま(襖)とは、木などでできた骨組みの両面に紙や布を張ったものでそれに縁や引手を付けたもの。
主に仕切りに使う道具を言います。
- ふすまの始まり
- ふすま(襖)の語源は、「衾所(ふすまどころ)」と言われる寝室の仕切りとして使われたことからだと言われています。
- ふすまと障子の違い
- 初めはふすまも「遮る物」として障子と呼ばれていましたが、平安時代以降に障子がより光を通す物とし「明障子」としてふすまと別れたたと言われています。
ふすまの開け閉め
- 開
-
- 1.ふすま(襖)の中央で正座をし、ノックの代わりに「失礼します」とお声をかけます。
- 2.引き手(ふすまの手をかける窪みまたは、取手)に手をかけ”5cm”ほど開き、親骨(枠)に手をかけ開閉を行います。
- 3.かけた手を親骨(枠)に添って下げ、自然と手の届く場所を押しながらふすまの中央まで開きます。
- なお、ここまでの動作で部屋の中の方とは目を合わせないようにします。
- 4.伸ばしている手を変え、身体通れるくらいか、”5cm”ほど閉じるための「手がかり」を残して開きます。
- 5.会釈をし、正座をしたまま拳を軽く握り両手で身体を支えながらにじって部屋へ入ります。
※にじる:千利休が考案した茶室の入り口「にじり口」が初めとされており、にじり口から入室する人は武士も商人も誰もが身分差に関係なく、同じように頭を下げて入室することと言われています。
- 閉
- 入室とは逆の作法となり
- 1.ふすま(襖)を向いて正座をし、ふすま(襖)に近い手で床から15センチほどの辺をつかみ、半分くらいまで閉めます。
この時、ふすま(襖)を開く時に残した「手がかり」をつかむようにします。
- 2.手を組み替え、ふすま(襖)を”5cm”ほど残し途中まで閉めます。
- 3.引き手を使い、ふすま(襖)を完全に閉めます。
豆知識
- 調湿機能
- ふすま(襖)は和紙と木骨芯が使われているため、湿度が高ければ除湿を、乾燥すれば排出を行う効果があります。
- ふすま(襖)の寿命
- ふすま(襖)の耐久性は長くて30年も使うことができます。
ただし、殆どが紙でできているため年月経過で色あせたりしてきます。
また日光に当たる場所はより寿命は早いです。
- 鴨居と敷居
- ふすま(襖)をすべらせるレールに当たる上の部分を「鴨居」、下の部分を「敷居」といいます。
長くふすま(襖)を使っていくと敷居の滑りが悪くなっていきますがこの時は敷居に蝋を塗ったり、専用のテープを貼ったりすると改善します。
なお、ふすま(襖)が歪んでいるのが原因で滑りが悪くなっている場合はふすま(襖)の周りも歪ませる原因となってしまうので早めの取り換えを推奨します。
過去のヒントはコチラ